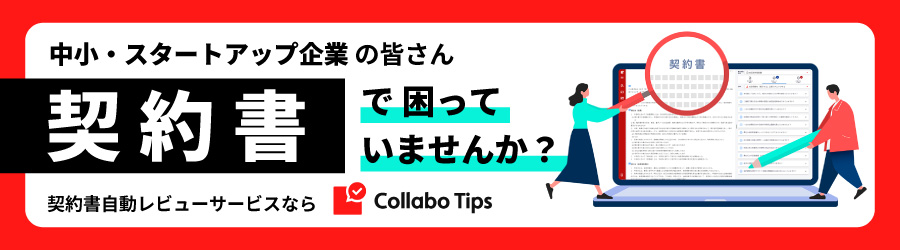【特許権譲渡契約書】リーガルチェックポイント|弁護士監修
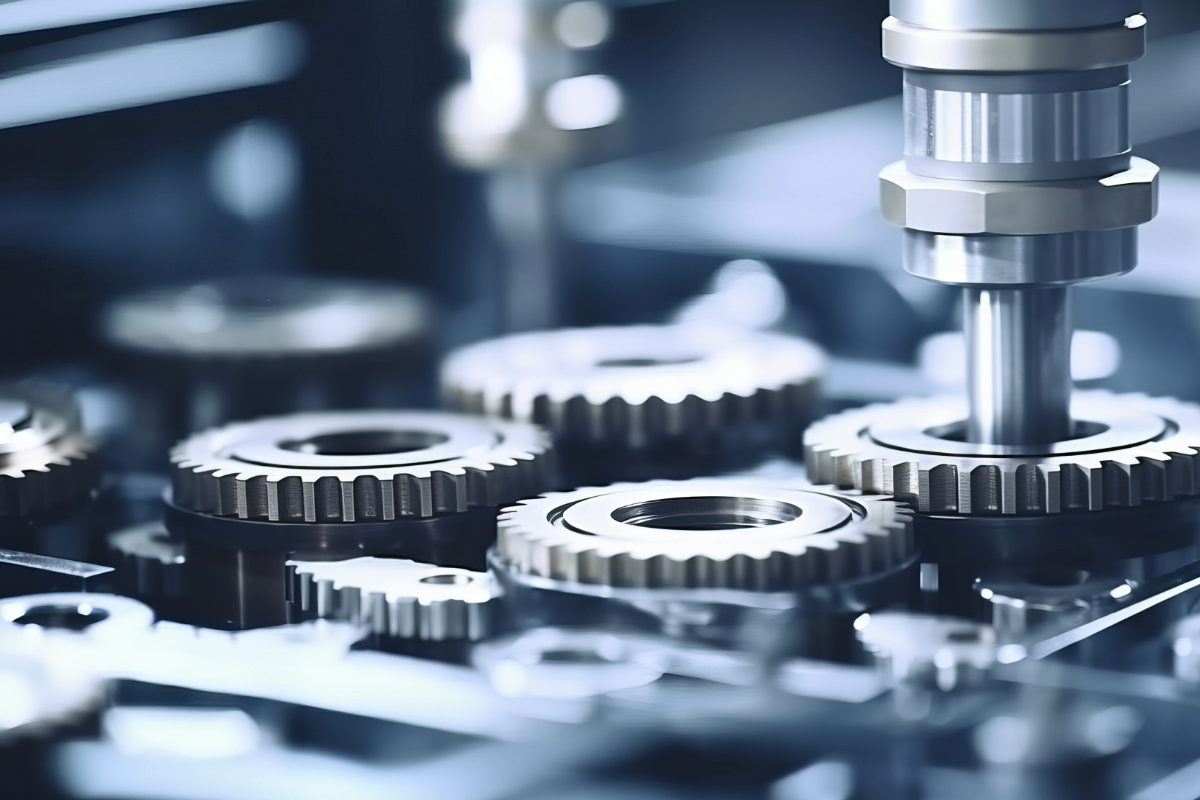
製品開発や事業戦略の一環として、他社が保有する特許権を譲り受けることがあります。しかし、第三者から特許権を譲り受ける際には、いくつかの法的留意点があります。特に、特許権は、目に見えない無体財産権であり、その内容は複雑です。また、権利の移転や使用に関する手続きが厳格であるため、契約書の内容やその後の手続きについて十分に理解しておくことが重要です。本記事では、特許権譲渡契約書を作成する際に必要なリーガルチェックポイントについて、契約書自動チェックサービス”CollaboTips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。
譲渡対象特許権についての調査・確認
特許権を譲り受けるにあたっては、十分に調査し、確認することが必要です。特許権の価値や譲渡の適法性を確保するため、以下の点を事前に確認しておくことが重要です。
1.特許原簿の確認
特許原簿に特許権の権利や権利内容、権利の存続期間などが記載されています。まずは特許原簿を確認し、以下の点を確認しましょう。
特許権者の確認
譲渡人が特許権を保有しているか、第三者に譲渡されていないかを確認します。
特許権の存続期間
特許権は最大20年間という存続期間があります(特許67条)。譲渡価格にも影響を与えるため、特許権の残存期間を確認します。
年金の支払い状況
特許の年金(特許料)が未払いの場合、特許権が消滅するリスクがあるため、年金の支払い状況の確認が必要です。
共有者の有無
特許が共有されている場合、譲渡対象の特許権全体を譲受けるためには、全ての共有者の同意が必要です(特許法73条1項)。譲渡人以外に他の共有者がいるかを確認する必要があります。
専用実施権の有無
特許権に関連する専用実施権の有無を確認します。但し、通常実施権は特許原簿に記録されていないので注意が必要です(特許法99条)。
異議申立てや無効審判の履歴
特許権に対して異議申立て(特許法113条)や無効審判(特許法123条)の対象となった場合、その決定の予告が特許原簿に記載されます(特登令3条3号、同4号)。これらの予告登録を確認することで、特許権が無効になるリスクや、異議申立てにより特許が取り消される可能性を把握することができます。但し、ここで分かる履歴は特許異議や無効審判の審理係属の有無のみです。無効審判等の有無にかかわらず、特許権には無効理由(未発見の先行技術文献)が存在する可能性がある点に注意が必要です。
2.特許原簿で確認できない情報
以下のような情報は特許原簿では確認できないため、別途調査や確認が必要です。
通常実施権の有無
通常実施権は特許原簿に記録されませんが、その通常実施権者は特許権を新しく取得した譲受人に対しても権利を主張できます(特許法99条)。そのため、新しい特許権者は、従前からいる通常実施権者の実施継続を認めざるを得ません。そのため、契約書や関連資料を通じて、その有無を確認する必要があります。
先行技術文献の調査
特許権は審査を経て登録されますが、審査段階で発見されていなかった先行技術文献は特許原簿や特許審査経過には記載されません。そして、特許権を行使する際には、被告側が新たに先行技術文献を提示してきて、無効理由を争うことがほぼ確実に発生します(特許法104条の3、特許法29条2項)。このため、特許を譲り受ける際には、先行技術文献が存在しないかどうかの調査が重要です。譲渡を受けた後に無効審判を受けるリスクを減らすためにも、譲渡対象特許の周辺技術や既存の先行技術について調査を行うことが推奨されます。
特許権の利用状況
特許権がどのように利用されているかの情報は特許原簿には記載されません。特許権を取得したとしても、事業化や商業化が成功するとは限りません。そのため、対象特許の実施状況等を事前に調査する必要があります。
海外特許の有無
日本の特許原簿では、海外の特許の情報を確認できません。譲渡対象特許が「ファミリー特許」として海外にも出願されている場合、別途調査が必要です。特に、当該特許を用いて海外でのビジネスを行う予定がある場合、海外特許の有無や登録状況は重要になります。そのため、譲渡対象特許の海外特許の有無等も調査を行うことが推奨されます。
3.特許情報プラットフォーム(J-Platpat)の活用
特許原簿は、誰でも閲覧することができますが、少し手続きが迂遠です。最終的に特許権の取得を決定した場合には、特許弁護士や弁理士に特許譲渡契約書の確認と併せて、特許原簿の確認も依頼することが推奨されます。しかし、未だ特許権の取得を悩んでいる段階で弁護士や弁理士に依頼するのが大変という場合、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)を用いて予備的に調査・確認をする方法があります。
譲渡対象特許権の譲渡手続き
特許権の譲渡において、譲渡契約書を締結した後には、特許庁での「移転登録」が必要です(特許法98条1項1号)。
| 特許権譲渡の合意 + 特許庁での移転登録手続 → 特許権の譲渡が有効 |
譲渡契約の合意が成立しても、移転登録が行われるまで、特許権は譲渡されたとは見なされません。この移転登録を経て、初めて譲渡の効力が発生し、第三者に対しても譲渡が公示されることになります。
具体的には、譲渡人と譲受人が特許庁に対して移転登録の申請を行い、譲受人が正式な権利者として登録される必要があります。そのため、譲渡契約書においては、この移転登録の義務を譲渡人と譲受人の双方に明確に記載しておくことが重要です。
特許権譲渡契約書のチェックポイント
特許権譲渡契約書には、譲渡対象特許権に関する詳細な情報や譲渡の条件、権利・義務の移転に関する取り決めを盛り込むことが必要です。以下は、特許権譲渡契約書で確認すべき主なチェックポイントです。なお、独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイトで、特許譲渡契約書のひな形や簡易チェックリストがダウンロードできます。
1.移転登録手続きに対する譲渡人の協力義務
譲渡人は、特許権移転のために必要な手続きを速やかに行う義務があります。この手続きが滞ると、譲渡が完了しないため、譲渡人は譲受人の要求に基づいて必要な書類や情報を提供し、速やかに移転登録手続きを進めることが求められます。
2.保証の範囲
譲渡人が行う保証に関しては、契約書において範囲を明確に記載する必要があります。譲渡人は以下のような保証の有無を明確にすることが望ましいです。
権利の所有権
譲渡人が譲渡対象特許権を正当に所有していることを保証します。
特許権の有効性
特許権が有効であり、無効化されるリスクがないことを保証します。
第三者権利の侵害
特許権が第三者の権利を侵害していないことを保証します。
実用化可能性
特許発明が商業的に実用化可能であることを保証する場合もあります。特許が実際に製品化できるか、技術的に実現可能であるかを確認します。
これらの保証の有無を契約書に明確に記載しておくことで、万が一問題が発生した場合の当事者間の責任や負担の所在を明確にしておくことで、後日のトラブルを低減できます。
3.譲渡対象特許権を実施するための技術指導等
譲受人が特許を実施するために必要な技術的サポートが必要な場合、その内容を契約書に記載することが必要です。特許権が高度な技術に基づく場合、譲渡人による技術指導やノウハウの提供が契約書で明確にされていると、譲受人が特許を適切に活用するための支援が確保されます。この場合、秘密保持条項が重要になります。
4.対価の不返還
特許権が無効になった場合に支払われた対価の返還の有無を契約書に含めることが将来のトラブル回避につながります。もし、契約書に「対価の不返還」に関する条項を盛り込だ場合、特許権が無効になったときに譲受人は譲渡人に対して返金請求ができなくなります。
海外特許に関連する留意点
譲渡対象特許権が日本国内に加え、海外特許も含まれている場合、以下の点に留意する必要があります。
契約書での譲渡合意
日本国内の特許権譲渡契約書で、関連する海外特許も同時に譲渡する旨を記載することは可能です。しかし、各国の特許法が異なるため、海外特許に関しては別途手続きを行う必要がある点を理解しておきましょう。
譲渡手続き
海外特許については、各国ごとに特許庁に移転登録手続きを行う必要があります。これにより、特許権の譲渡が正式に認められます。
準拠法と管轄
特許権の譲渡契約書には、準拠法や紛争解決方法(管轄裁判所や仲裁機関)を定めておくことが望ましいです。日本国内の特許権については、日本法に基づいて紛争が解決されることが一般的です。また、紛争解決に関しては、日本の東京地方裁判所または日本での仲裁を指定することが推奨されます。
まとめ
特許権の譲渡契約は、譲渡対象の特許権に関する詳細な情報収集と慎重な手続きが求められます。ファーストステップとしては、特許原簿の確認(または、それ以前の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の確認)が重要ですが、特許原簿に記載されていない情報にも注意が必要です。例えば、通常実施権の有無は特許原簿では確認できず、契約書などの書類を通じて確認する必要があります。また、先行技術文献や、海外特許に関連する情報も調査が必要です。そして、何よりも、取得した特許権が絵に描いた餅にならないように、特許発明の実用化、商業化の可能性も十分に調査しましょう。そのうえで、譲渡契約では、事前調査の結果に基づいて、譲渡対価や保証の範囲等の条件を明確にすることで、特許権譲渡に関するリスクを最小限に抑え、特許権譲渡の成功確率を上げることができるでしょう。
コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所
メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。