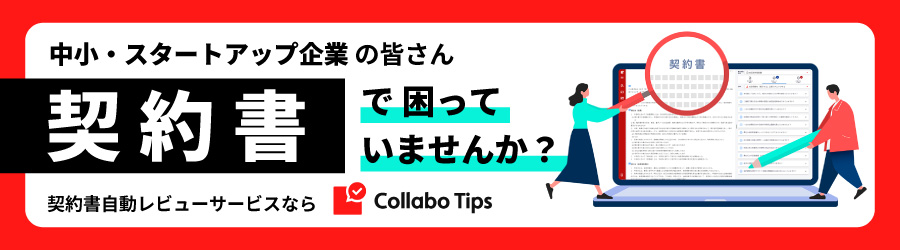【製造委託契約書】リーガルチェックポイント6点とは | 弁護士監修
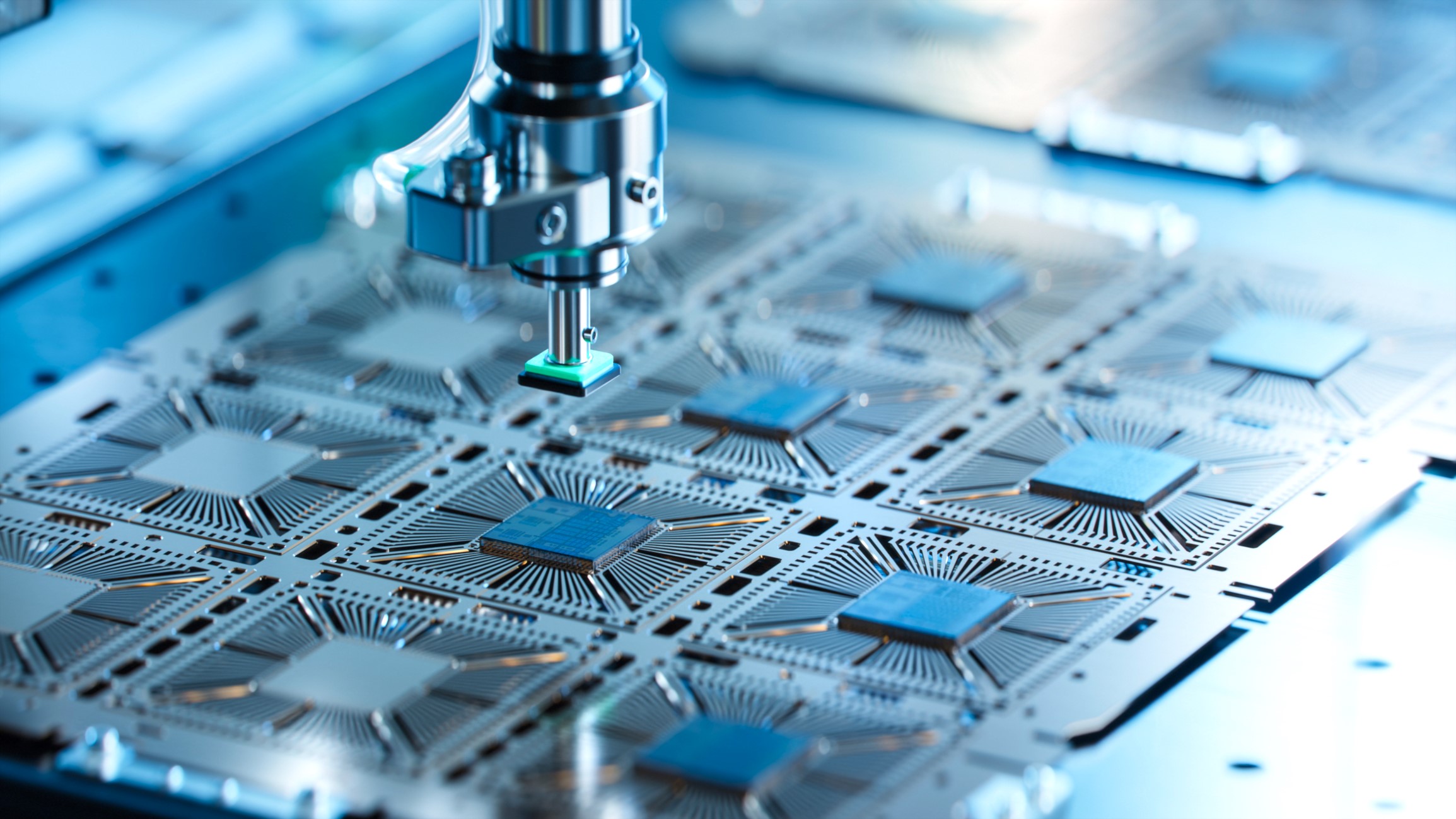
製造委託契約とは、製品の製造を外部の業者に委託する際に必要不可欠な契約です。この記事では、主に中小企業やスタートアップ企業の法務担当者が、製造委託契約書を交わす際にチェックすべきポイント6点と関連するモデル条項について、契約書自動チェックサービス”Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。
ポイント1:製造対象「仕様」が明確になっているか
製造対象「仕様」で、何を作るのかを明確にすることが重要です。もし「仕様」が不明確な場合、製品の完成の有無をめぐってトラブルが発生することがあります。具体的には、「そもそも何を作る約束だったのか」や「それはできているのか」という点が争いとなります。このため、以下の2つの要素を明確にしておくことが重要です。
① 製造対象(何を作る約束なのか)
② 納品検査基準(当該製品が完成しているのかの判断基準 )
これらを明確に定義することで、多くの紛争を未然に防ぐことができます。
【サンプル条項】
第1条(製造対象品)
受託者は、委託者が指定する以下の仕様に基づいて製造するものとする。
1. 製品名:〇〇〇〇
2. 材質:xxxx
3. サイズ:yyyyy
第2条(納品検査基準)
納品された製品は、以下の基準に基づき検査されるものとする。
1. 寸法:±〇〇mm以内
2. 材質の確認:xxxxx
3. 機能テストの合格基準:zzzzz
なお、委託者(発注者)の「仕様」が不明確な場合は、技術開発契約に切り替えることを検討しましょう。
ポイント2:仕様変更が生じた際の対応
仕様変更が生じると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 対価の不一致:仕様変更によって製造コストが変動する場合、対価について合意が得られないと、受託者が不利益を被る可能性があります。
- 納期の遅延:仕様変更が必要な場合、追加の時間が必要となり、納期に影響を及ぼすことがあります。これにより、委託者の業務に支障が出ることも考えられます。
- 品質問題:仕様変更に伴い、受託者が新たな技術や材料を使用することになり、品質が安定しない場合があります。これが納品後の不適合に繋がるリスクがあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、仕様変更に備えた手続きや対価の取り扱いについては、契約書に記載しておくことが安全です。
【サンプル条項】
第〇条(仕様変更)
1 委託者は、必要に応じて製品の仕様を変更することができる。
2 仕様変更に伴う対価は、委託者と受託者との間で別途協議の上決定するものとする。
3 受託者が仕様変更により製造が困難になる場合、契約を一時停止することができる。この場合、各当事者は相手に対して契約の一時停止に伴う損害賠償等を行うことができないものとする。但し、受託者は委託者に対してそこまでに行った仕事の割合に応じた対価の支払いを求めることができる。
ポイント3:納品後の契約不適合責任
製造委託基本契約は請負契約又は売買契約であると考えられます。そのため、納品後に製品に不適合が生じた場合の受託者の責任は、民法によれば納入後1年間となります。しかし、商法の商人売買の規定が適用(類推)されて、不適合責任の期間が6か月と短くなることがあり得ます。そのような解釈上の疑義を無くすためにも、契約書において契約不適合責任の期間を明記することが望ましいです。
【サンプル条項】
第〇条(契約不適合責任)
1 受託者は、委託者に対し、個別契約で定める仕様に従って本業務を遂行の上、納入物件を作成したことを保証する。
2 委託者は、目的物の検収後後、目的物の種類、品質又は数量が本契約又は個別契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)を発見し、発見後〇か月(※)以内にその旨を受託者に通知した場合には、受託者に対し、契約不適合を理由とする目的物の修補、代替品若しくは不足分の引渡し(以下、「履行の追完」と総称する。)又は代金の減額のうちから一つ又は複数の手段を選択し、これを請求することができる。ただし、個別契約において、受託者が下請法でいう下請事業者に該当する場合には、下請法の定める範囲で受託者は本条の責任を負う。
3 前項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
※契約不適合責任の当該期間が数か月以内の場合、やや期間が短いため受託者に有利であり、逆に1年以上になると、やや期間が長いため委託者に有利であると考えられます。
ポイント4:製造物責任
納品した製品に欠陥があることが原因で消費者など第三者に損害を与えた際、委託者と受託者のどちらが責任を負うのかが問題になり得ます。そのため、製造物責任の所在を契約で明らかにしておくことが考えられます。 適正なリスクヘッジのため、製造物責任(PL)に関しては、受託者がPL保険を付保する義務を規定することが多いとも考えられます。
【サンプル条項】
第〇条(製造物責任)
1 当事者は、本製品の欠陥により、第三者に損害が生じ、又はそのおそれがあると認めた場合、直ちに相手の当事者に通知する。この場合、当事者は協議の上、原因の調査、当該欠陥の除去及び損害発生防止のために必要な措置を取る。
2 本製品の欠陥(製造物責枉法第2条第2項にいう欠陥をいい、以下も同様とする。)に起因して、本製品又は本製品を使用した製品が第三者の生命、身体又は財産等に対し損害を与えたことにより、委託者が当該第三者から損害賠償を請求された場合には、受託者が当該損害(弁護士費用を含むが、これに限らない)を賠償する。
3 受託者は、自らの費用負担により、本条の責任を担保するために合理的に必要な製造物賠償責任保険に加入する。なお、受託者は、委託者から求められた場合には、当該保険の加入を証する書面の写しを速やかに委託者に提出する。
ポイント5:第三者との紛争に関する責任
製品について、第三者の権利を侵害する等の紛争が生じた場合の責任については、2024年10月に中小企業庁が知的財産取引ガイドラインを改定し、委託者(通常は、大企業を想定)が受託者(通常は、中小企業を想定)に、一方的に責任を転嫁することが無いように、以下のようなモデル条項が公開されています。
【中小企業庁の知的財産取引ガイドラインのモデル条項 】
第8条 (第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応)
1 本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品(以下、「目的物等」という。)について、目的物等に起因して第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたときは、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。
2 前項の紛争の解決に係る負担について、甲及び乙は、当該知的財産権の侵害に係る自らの責任の範囲において当該負担の責任を負う。
上記8条2項を見ると、各自の責任と定められています。これは情報やアイディアを出した当事者が自己責任を負うという考え方がベースにあります。ただし、上述した通り、製造委託契約は発注者が仕様を決めていることを前提とするため、通常は発注者側が責任を負うことになる可能性が高いとも考えられます。そのため、中小企業庁の知的財産取引ガイドラインでは、次の通り、もし受託者が、第三者から権利侵害の賠償を求められた場合、それが委託者の指示に基づくときは、委託者に対して求償を求められるとされています。
【発注者による指示内容等の開示、求償等】
受注者に帰責事由がないにもかかわらず、第三者が受注者を相手に訴訟を起こしたときは、原則として、発注者は、受注者からの、目的物の仕様等の決定に係る経緯や受注者 に対する指示の内容等を開示する旨の要請や、当該紛争によって受注者に生じた第三者への損害賠償についての求償等に応じなければならない
知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について | 中小企業庁
ポイント6:意図しない技術提供(ノウハウ流出)に注意
受託者は、委託者の要求以上の情報を提供する必要はありません。契約書においても、意図しない技術提供を避ける条項が必要です。中小企業庁の知財取引ガイドラインには、次の通り、受託者の秘密情報は受託者に帰属すること(1項)、受託者は秘密情報の開示義務を負わないこと(2項)、その他、受託者は、その保有する知的財産権の提供義務を負わないこと(3項)が定められています。
【知財取引ガイドラインのモデル条項】
第6条 (確認事項)
1 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利益も相手方に与えられるものではない。
2 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。
3 甲及び乙は、本契約及び原契約が、乙が有する固有知的財産権等の開示、提供の義務を負うものではないことを確認する。乙が有する固有知的財産権等の開示、提供を行う場合には、対価を含め、別途協議する。
以上のチェックポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 なお、契約の各サンプル条項や注意事項については、Collabo Tipsの自動チェックでも確認することができます。
契約書チェック「コラボ・ティップス」とは
メリットパートナーズ法律事務所が監修する契約書チェック自動サービス “Collabo Tips”[コラボ・ティップス]は、新しいビジネスをつくりたい中小企業の法務担当者に伴走します。「オンラインで」「だれでも」「簡単・自動で」使えるのが特徴です。契約を「バトル」にせず、迅速なコラボレーションを進めるために、あなたの立場に立って助言します。無料プランでも契約書7種類をチェックできます。
コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所
メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。