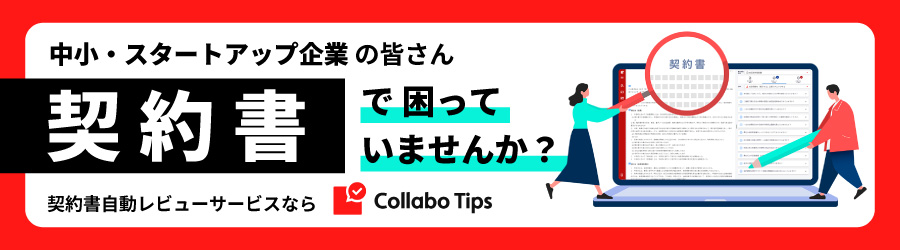【業務委託契約書】リーガルチェックポイント|弁護士監修

業務委託契約書は、企業が他の企業やフリーランスに業務を委託する際に重要な役割を果たします。この契約書は、双方の権利と義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐための基盤となります。この記事では、業務委託契約書を作成・確認する際のリーガルチェックポイントについて、契約書自動チェックサービス”CollaboTips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。
業務委託契約とは
業務委託契約書は、企業が行う業務を外部の第三者に委託する場合に用いる契約書です。業務委託契約は、業務の内容に応じて、「請負契約」と「委任契約」(準委任契約)に分けられます(または、1つの契約書の中に、双方の性質を有する業務が併存する場合もあります)。
|請負契約
請負契約は、受託者がある仕事を完成することを約束し、委託者(依頼者)がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。
例)建築契約:建物の建築という仕事の完成を委託する契約。
機械保守契約:工場機械やエレベータ等の保守を委託する契約。
運送契約:物品や旅客の運送を委託する契約。
|準委任契約
準委任契約(又は委任契約)は、依頼者が何かの事務を処理することを受託者に委託するものです(民法643条、民法656条)。「仕事」の完成を目的とするものではないことが特徴です。
例)コンサルティング契約:コンサルタントに専門的な知識・経験等を活かした業務を委託する契約。
弁護士との契約:弁護士に法律事務を委託する契約。
業務委託契約書では、次の通り、それが請負契約であるのか、委任契約であるのかにより、報酬体系が異なるため、いずれの契約であるのかを確認したうえで、契約書をチェックすることが重要です。
委託業務の内容
委任業務の内容は、さまざまなものがあります。しかし、どのような業務であっても、委託する業務の成果が明確になっているか否かを確認するが重要です。もし、成果の判定基準が不明確な場合、請負契約ではなく、委任契約とすることを検討しましょう。もし、請負契約としてしまうと、成果の評価基準が曖昧であると、仕事の完成の有無について委託者と受託者で認識にズレが生じやすいためです。成果の評価基準が定まらない例として以下のような契約があります。
|成果の基準が不明確になりやすい契約の例
・開発委託契約:開発を委託する契約。開発対象の性能や製品化の実現可能性が定まらない。
・デザイン業務委託契約:商品のデザインを委託する契約。デザインは主観に左右されやすく、言語化が難しい。
報酬の種類
業務委託契約には、委任契約と請負契約の2種類がありますが、これに基づく報酬の支払い方法は大きく以下の4種類に分類できます。
(1)成果報酬型:成果の品質や量に応じて報酬が変動するもの
(2)単発報酬型:単発の業務について定額の報酬が支払われるもの
(3)定期払い型:定期に定額の報酬を支払うもの
(4)時間払い型:業務時間に応じて報酬が決まるもの
それぞれの報酬体系には、次の表の通り、委任契約や請負契約に向き不向きがあります。適切な契約形態と報酬体系を選ぶことが重要です。
|成果報酬型
成果報酬型は、成果物の評価基準が事前に明確に定義され、その基準に基づいて報酬が変動する体系です。たとえば、弁護士への訴訟委任契約では、裁判で認容された金額の16%を成果報酬と定める場合があります。このように、成果基準が明確であることが最も重要な要素となります。
委任契約には適しています。例えば、弁護士やコンサルタントなどが契約に基づいて特定の成果を上げる場合、成果基準を設定することで報酬が決定します。
請負契約には、成果基準が明確でも、成果達成の見通しが不確実な場合には不向きです。たとえば、開発委託契約やデザイン委託契約では、成果基準の明確化が難しく、進捗管理の調整が求められるため、請負契約で成果報酬型を適用することは難しいことがあります。なお、この場合、成果を多段階に分割して、特定のマイルストーンごとに成果報酬を支払うマイルストーン払いを採用することも考えられます。
|単発報酬型
単発報酬型は、1回限りの業務に対して報酬が定められる体系です。例えば、法律相談や調査業務など、短期間で完了する業務に適用されます。
委任契約には、業務内容が明確で、特定の成果物が求められる場合に適用可能です。法律相談や一回限りの業務などが該当します。
請負契約にも適用できますが、契約内容が明確であることが前提です。小規模な業務で、例えば、納期が数か月以内で、成果基準を明確にしやすい業務(例えば、戸建ての設計図面の製図)などに向いています。
|定期払い型
定期払い型は、契約期間内に定期的に報酬が支払われる体系です。長期契約や進行管理が必要な業務に適用されます。たとえば、システム開発や保守契約など、長期的な業務遂行に伴う支払い方法です。
委任契約には向いています。特に長期契約や定期的な業務を遂行する場合に適用されます。顧問契約などが代表例です。
請負契約には適用する際に注意が必要です。進行中の支払いが求められる業務には適していますが、たとえば、システム開発のプロジェクトが契約期間内に未完成の場合の支払い調整が求められます。
|時間払い型
時間払い型は、業務時間に応じて報酬が支払われる体系です。弁護士への委任契約やコンサルティング契約など、成果物が定義されない場合に適用されます。
委任契約には適しています。業務が時間単位で進行し、成果物が明確に定義されていない場合に適用されます。弁護士への委任契約やコンサルタント契約などが該当します。
請負契約には不向きです。請負契約は、仕事が完成した時点で報酬が支払われるため、時間単位で進行する契約とは相容れません。仕事が完成しないと報酬が支払われないという契約の性質と矛盾します。
報酬体系と契約形態の対比表
| 報酬体系 | 委任契約に向いているか | 請負契約に向いているか | 備考 |
| 成果報酬型 | ○(成果基準が明確な場合) | △(達成見通し不確実な場合に注意) | 成果の内容が変動し、それに応じて報酬も変動。 |
| 単発報酬型 | ○(短期向き) | ○(短期向き) | 1回限りの業務(例:法律相談、調査)に適用。 |
| 定期払い型 | ○(定期的な業務向き) | △(契約期間内の未完成時の支払い調整が必要) | 長期契約や進捗管理が必要な業務に適用。 |
| 時間払い型 | ○(業務の過程が重要) | ×(請負契約には不向き) | 成果物が定義されない場合に適用。 |
その他の注意点報酬体系の適用に関する整理表
|成果の権利
業務の遂行過程で生じた成果の著作権等の権利が誰に帰属するのかを確認しましょう。もし、受託者に権利が帰属する場合や従前から受託者にある権利が成果に含まれている場合、委託者は受託者からの利用許諾を得ておく必要があることに気をつけてください。
|秘密情報、個人情報の取り扱い
秘密情報の流出や個人情報の漏洩を防ぐために、秘密保持義務や個人情報の取り扱いについて契約書に定めましょう。
|損害賠償
業務遂行における損害賠償の範囲や責任について確認しましょう。
違約金を定めるサンプル条項
第〇条(違約金)
一方の当事者が、本契約に違反して相手の当事者に損害を与えた場合は、相手の当事者に対し、違約金〇〇円を支払う。ただし、当該違反により相手の当事者に生じた損害が本違約金額を上回る場合、違反をした当事者は、その超えた部分についても賠償する。
損害賠償の責任を限定するサンプル条項
第〇条(損害賠償の範囲)
1 両当事者は、本契約に違反して相手の当事者に損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を与えたときは、相手の当事者に対して当該損害を賠償する責任を負う。
2 前項の損害賠償の累計総額は、本契約の委託料を限度とする。
|フリーランスとの契約の場合、労働契約になっていないか?
フリーランスの業務委託契約では、フリーランスが実質的に「労働者」と判断されると、労働基準法等が適用される可能性があることに注意が必要です。労働基準法等が適用された場合、例えば、フリーランスが1日8時間を超えて働いたときや深夜労働を行ったときに割増賃金が発生する等の可能性が考えられます。
フリーランスが労働基準法等の「労働者」に該当するかどうかの判断基準は、①労働が他人の指揮監督下において行われているか、②報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか、という2つの基準で判断されることとなります。請負契約や委任契約といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されることが想定されます。労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。
参考:厚生労働省 労働基準法における「労働者」とは
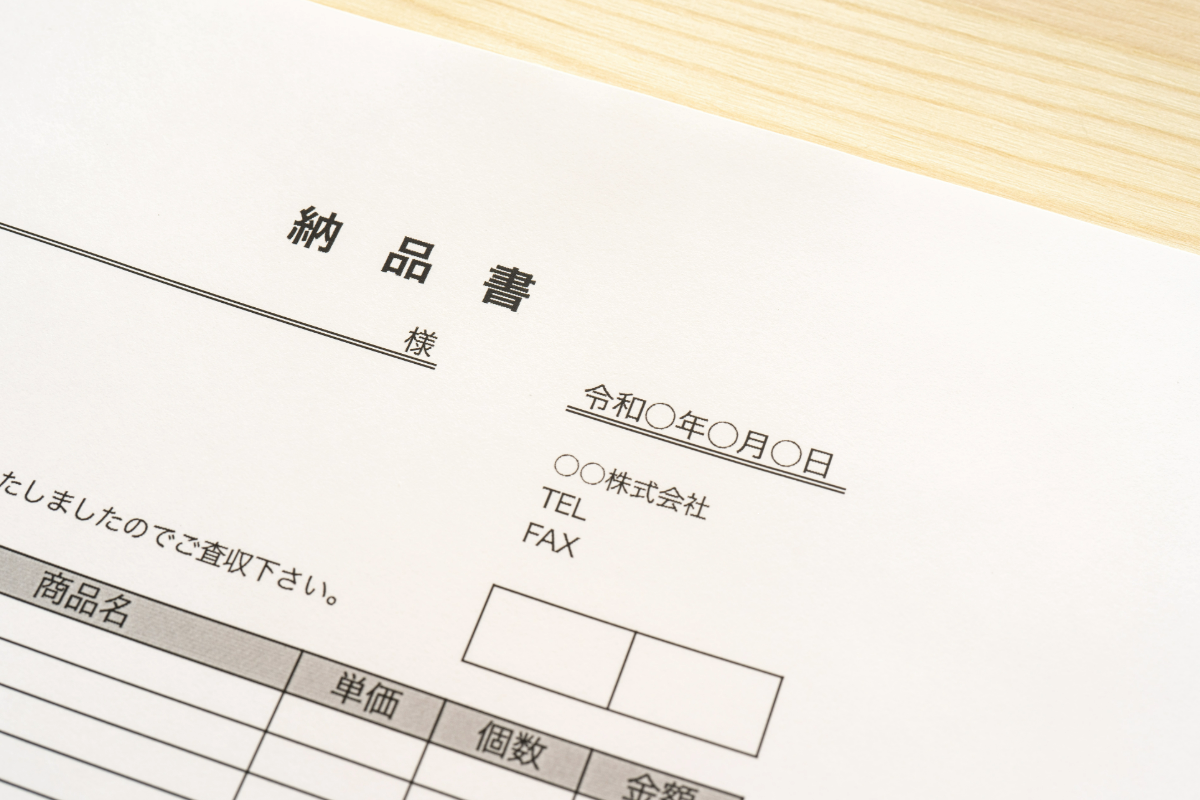
まとめ
業務委託契約書は、依頼者と受託者が円滑に業務を進めるための重要な契約書です。内容をしっかりと確認し、双方が納得できる条件で契約を締結することが、トラブルを防ぐための最良の方法です。上記のチェックポイントを参考に、契約書を慎重に作成・確認することをお勧めします。
コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所
メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。